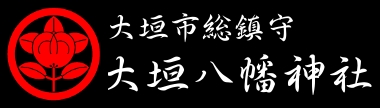御祈祷は毎日午前9時~午後4時まで受け付けております。
ご本人が参拝出来ない場合は、家族や友人による代参にてお申し込みできます。
個人の御祈祷は、予約は不要ですが、団体参拝、挙式、神社行事でお受けできない時間帯もございます。
できるだけ事前にホームページや社頭でお知らせいたしますが、待ち時間が長くなる場合もございますので、ご了承下さい。
法人団体は、事前に御予約下さいますよう、お願い申し上げます。
※御祈祷に関してのお問い合わせは電話にてお尋ね下さい。
御祈祷料
●個人 五千円以上・一万円以上
●法人団体 一万円以上・二万円以上・三万円以上
ただし、交通安全祈願のみ、車両1台につき五千円以上
御祈祷の種類
- 初宮参り
- 安産祈願
- 交通安全
- 家内安全
- 七五三
- 厄祓い
- 健康祈願
- 病気平癒祈願
- 八方除
- 勉学向上
- 試験合格
- 必勝祈願
- 良縁祈願
- 商売繁盛
- 事業繁栄
- 工事安全
- その他諸祈願 (お受け出来ない場合もあります)
初宮参り
赤ちゃんが神さまの御加護を戴き無事に誕生したことに感謝し、これからも健やかに成長するように願い初めてお宮参りすることをいいます。
一般的には男子は生後三十一日目、女子は生後三十三日目にお参りするのですが、あまり日数にこだわらずに、予約等は必要ありませんので赤ちゃんの事を考え暖かい日や天気のよい日を選んでお参りするのがよいでしょう。
※お宮参りには、赤ちゃんを産土(氏神・鎮守)さまの産子(氏子)として認めていただく意味があります。
安産祈願
出産にあたり、お母さんと赤ちゃんの無事と、お産が軽くなるように祈願する儀式です。
安産祈願は「着帯の祝い」の日に合わせて行うことが多いのですが、着帯の祝いとは、赤ちゃんの健やかな発育を願、妊婦が腹帯(岩田帯)を締めるお祝いの事です。
懐妊5ヶ月目の「戌の日」を選ぶのは、犬のお産が軽いことから安産にあやかりたいという願いからだと言われております。
御持参頂きました腹帯に、御朱印を押して御神前にお供えし、お祓いをいたします。腹帯を1~2点御持参下さい。
神社に腹帯の御用意はございません。
また腹帯は、さらし、ガードルいずれでも結構です。
| 令和8年 戌の日カレンダー | |
|---|---|
| 1月 | 12日(月)・24日(土:大安) |
| 2月 | 5日(木:大安)・17日(火) |
| 3月 | 1日(日)・13日(金)・25日(水) |
| 4月 | 6日(月)・18日(土)・30日(木) |
| 5月 | 12日(火)・24日(日:大安) |
| 6月 | 5日(金:大安)・17日(水)・29日(月) |
| 7月 | 11日(土)・23日(木) |
| 8月 | 4日(火)・16日(日)・28日(金) |
| 9月 | 9日(水)・21日(月) |
| 10月 | 3日(土)・15日(木)・27日(火) |
| 11月 | 8日(日)・20日(金) |
| 12月 | 2日(水)・14日(月)・26日(土) |
赤色は日曜祝日
七五三
3歳、5歳、7歳の節目に、お子様の健やかな成長を祈願いたします。
男子は3歳、5歳。女子は3歳、7歳にお参りするのが一般的ですが、近年はあまりこだわらずに3歳から7歳までのお子様がお参りされます。
本来は数え年で行いますが、現在は満年齢で行うご家庭も増えております。
| 令和8年 七五三早見表 | ||
|---|---|---|
| 年齢 | 数え歳 | 満年齢 |
| 7歳 | 令和2年生まれ | 平成31年生まれ |
| 5歳 | 令和4年生まれ | 令和3年生まれ |
| 3歳 | 令和6年生まれ | 令和5年生まれ |
厄と厄年祓い
| 令和8年 厄年早見表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 性別 | 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 男 | 61歳 | 昭和 42年生 |
昭和 41年生 |
昭和 40年生 |
| 42歳 | 昭和 61年生 |
昭和 60年生 |
昭和 59年生 |
|
| 25歳 | 平成 15年生 |
平成 14年生 |
平成 13年生 |
|
| 女 | 61歳 | 昭和 42年生 |
昭和 41年生 |
昭和 40年生 |
| 37歳 | 平成 3年生 |
平成 2年生 |
平成 1年生 |
|
| 33歳 | 平成 7年生 |
平成 6年生 |
平成 5年生 |
|
| 19歳 | 平成 21年生 |
平成 20年生 |
平成 19年生 |
|
「厄」とは、「災難」とか「わざわひ」の事で、「わざ」は鬼神のなす行為、「はひ」は延べの義で長引くと言う意味です。
即ち、身に心配、難義、疾病、その他不意の悪事が長く降りかかること。また、不吉の気運、災難に逢うべき回り合わせであり、災厄・厄年・厄月・厄日等、色々な厄があります。
「厄」には、不意に降りかかる災禍(わざわひ)の他に、人がある年齢に達すると、災難を受け易いと言われる「厄年」とがあります。
これらの「厄」を祓い、吉に転ずる手だてを、「厄年」「厄祓い」とか「厄落とし」と言います。「厄祓い」の方法には、社寺に詣でて祈願する例が多く、特に神社では厄除の祈願祭を執り行ないます。
「厄年祓い」とは、厄年に当たる人が祓いを受ける事を「厄年祓い」と言い、普通の「厄祓い」とは区別をしています。
「厄年祓い」には、男子(25歳・42歳・61歳)、女子(19歳・33歳・37歳・61歳)を特に大厄と言われ、その前後の年も前厄・後厄として恐れ慎む習慣が一般に定着しています。
このような年回りは肉体的にも精神的にも大きく変化する転換期で、種々の災難をお起こし易く、また、受け易いので人生の節目に神社に参拝し、大神様の神威を仰ぎ、その御神徳により災厄を取り除いてもらう訳です。
令和8年の厄年については、右記表を御参照下さい。
八方塞
| 令和8年 八方塞早見表(一白水星) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 令和8年生 | 平成29年生 | 平成20年生 | ||
| 平成11年生 | 平成2年生 | 昭和56年生 | ||
| 昭和47年生 | 昭和38年生 | 昭和29年生 | ||
| 昭和20年生 | 昭和11年生 | 昭和2年生 | ||
八方塞とは、四方八方どの方角に向かって事を起こしても、良い結果が生まれない年廻りの事です。
令和8年の八方塞については、右記表を御参照下さい。